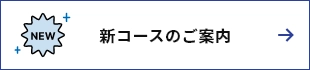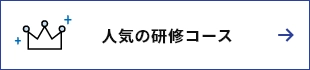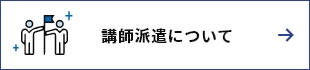「苦手」や「相性の悪さ」を克服して、確かな成長につながる人材育成を図る「部下を知るメガネ」研修とは?
- 記事公開日
- 2025.09.10

この記事のポイント
少子高齢化による社会的な人手不足や働き方・価値観の多様化などが進む近年、組織としての高い成果を目指すためには、幅広い人材との協働が重要となっています。多彩な人材の活用から、労働力の確保や新たな価値創出が求められる現代では、管理職としてはさまざまな部下たちのやる気を引き出すマネジメントが不可欠。部下ごとに属性や考え方なども大きく異なるなかで、それぞれが本領を発揮できるマネジメントをするためには、豊かな観点(部下を知るメガネ)を持って個々に関わる必要があります。
この記事では、3時間で学べる研修「部下を知るメガネ(017)」の内容をご紹介します。
「部下を知るメガネ」から誰もが成長できるマネジメントを実現
さまざまな部下を持つなかで、仕事観や考え方などの違いから、どう接したらいいのか悩むことは珍しくありません。また信頼関係やコミュニケーションの不足により、特定の部下に対する理解が浅いことで、なんとなく「そりが合わない」と認識してしまう場合も。苦手だと感じてしまうメンバーがいると、無意識のうちに偏った見方になり、部下ごとに育成の仕方や度合いが変わってしまう可能性もあります。人と人との関わり合いでは、どうしても個人ごとに相性の差は出てきてしまいますが、そうしたなかでも公平に部下を育てるのに重要なのが「部下を知るメガネ」です。「部下を知るメガネ」とは、より豊かな観点から、一人ひとりの向上心が湧き上がる動機を見出すことを指します。この「部下を知るメガネ」を持つことで、次のような効果につながり、一人ひとりの成長を促します。
適切な評価やフィードバックができる
「部下を知るメガネ」により、豊かな視点から相手を理解しようとする姿勢を持つことで、苦手な部分だけにとらわれない公平な評価ができます。一人ひとりに対する俯瞰的な評価から、個々にとって必要な改善点や前進した部分、伸ばすべき強みなども適切に見極められます。
部下のモチベーションを高められる
「部下を知るメガネ」をもとに、一人ひとりの動機づけを把握しておくことで、個々の前向きな姿勢を促す役割分担やアドバイスもしやすくなります。「部下を知るメガネ」により、それぞれにとっての意欲を促すポジションやチャンスを与えることで、モチベーションも高まり、部下自身が成長しようとする向上心にもつながります。
動機の源泉を見出して一人ひとりにとってベストな育成を図る
「部下を知るメガネ」を持つ大きな目的は、さまざまなタイプの部下がいるなかでも、一人ひとりに適した育成をすることにあります。部下それぞれの動機づけの方法を把握して、個々の成長意欲につながるコミュニケーションやフィードバックをするための根本的な考え方となるのが「部下を知るメガネ」です。本研修では、次のようなポイントから、部下全員の成長の可能性を伸ばしていく手法を学びます。
日々の対話やフィードバックから動機の源泉を探求
部下のさらなる成長に向けて重要なのは、日頃の対話やフィードバックのなかで、小さな変化や前進を認めながら個々の動機づけを促していくこと。そこで本研修では、こうした部下の高い意欲につながる、動機の源泉を知るためのコミュニケーション方法を学びます。なおプログラム内では、部下の向上心を高めるために、まずは「人は誰でも必ず成長できる可能性を持っている」という視点から習得。もし苦手な部下がいるなら、そう感じる原因を見つめ直すワークから実践します。
そして次のステップとして、部下の成長の促進を図るコミュニケーションやフィードバックの手法を学習。部下の動機の源泉を把握できるような対話の仕方を身につけていきます。例えば普段の会話のなかで、趣味・学生時代・過去のキャリアなど今までの経験に関する話題から、目を輝かせて話す内容が出てくることも。それこそがまさに動機の源泉であり、「部下を知るメガネ」による豊かな観点につながっていきます。
受講者の声
本研修を通じて、個々の育成を促す「部下を知るメガネ」の基本的なポイントを学ぶ効果として、次のような受講者の声も上がっています。
- 部下にレッテルを貼らず、自分と違う価値観を持っている存在と捉え、部下を見る視野を広げることが大切だとあらためて感じました。職場では業務の会話以外にも日頃の会話から、部下のやる気スイッチを探ってみようと思います。
- さっそく学んだテクニックを使い、社内で部下との1on1ミーティングの際、「過去に担当した案件で、最も印象に残っているものは?」といった質問をするようにしたところ、皆一様に饒舌に生き生きと話し始める姿が見られました。
まとめ
「部下を知るメガネ」の考え方は、一人ひとりの活躍や成長の促進、誰もが高いパフォーマンスを発揮するための人材育成に欠かせません。また「部下を知るメガネ」を通じて、メンバー全員のさらなる育成を図ることで、より多様な人材活用にもつながります。部下の育成に一層注力していきたい場合には、ぜひ本記事を活用してください。
◆本記事でご紹介した研修