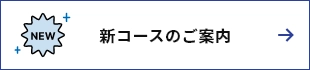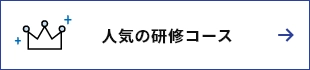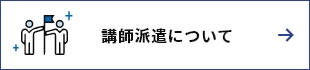部下や後輩のやる気を削がずに、正しく現実を見つめて改善や高みを目指せるフィードバックの基本研修とは?
- 記事公開日
- 2025.07.04

この記事のポイント
フィードバックは、日常的な定期面談(1on1)において、部下や後輩が自分自身で現状を理解して主体的な行動に移せるように促すものです。評価や指示を下すのではなく、部下や後輩が客観的にどのような状況にあるのかを的確に示し、さらなる成長に向けた取り組みへのヒントを与えるのがフィードバックの目的でもあります。
この記事では、3時間で学べる研修「フィードバックの基本(136) 」の内容をご紹介します。
誤ったフィードバックが部下や後輩のやる気を奪う?注意したい失敗例
きちんとフィードバックの場を設けていても、間違った方法で進めてしまうと、相手のモチベーション低下やストレスにつながってしまうケースもあります。よくある誤ったフィードバックのパターンとして、次のような例が挙げられます。
あいまいな表現で具体的な指摘がない
例えば、業務目標の未達成に対するフィードバックを行う場合。ただ表面的な結果だけを見て、「もっと頑張ろう」「やる気があったらできたのでは?」など、抽象的な言葉を投げかけてしまうケースも見られます。目標達成に向けてどう行動できたのか、どのような状況から未達成になったのかなど、客観的な視点からの深掘りができていないとフィードバックの内容もあいまいになりがちです。こうしたフィードバックでは、相手側にとっては次の段階で何をすべきか考える機会にならず、ただ否定されたように感じてしまうことも想定されます。
感情的に相手を責めるような言葉を使う
仮に部下や後輩がミスをしてしまった場合、怒りや苛立ちから感情的なフィードバックになってしまうケースも。ミスにつながった原因や対処法の指摘をせずに、例えば「自覚が足りないのでは」「普通なら○○はしない」など、相手を責めて委縮させてしまうパターンも見られます。こうした言葉を使ってしまうと相手のプレッシャーになってしまい、正しく現状を振り返るための情報共有や相談につながらず、的確なフィードバックもできなくなってしまいます。
一方的な意見だけを押し付けて相手を認めない
次のステップにつなげるためのアドバイスは重要ではあるものの、結果的には相手に強制してしまうケースも見られます。現状からの改善点の指摘は必要ですが、きちんと相手が納得して実行できるものでないと、ただ「やらされている」だけになってしまう可能性も。フィードバックでは、よかった行動や期待している部分はきちんとほめて認めつつ、相手を尊重する姿勢も大切です。
正しいフィードバックに向けて重視しておきたいポイント
先行きの見えないVUCAの時代を迎え、また働き方の多様化も進む昨今では、雇用する企業側で各人材のキャリアを保証するのが難しくなっています。こうした背景からも近年は、個々が自ら経験を積んで学びながら、理想の将来像を目指すキャリア自律が注目されています。こうしたキャリア自律を図るには、部下や後輩が成長しやすい環境につながる、効果的なフィードバックも重要です。そこで本研修では、部下や後輩のキャリア自律を促す、フィードバックの基本的な手法を習得。次のようなポイントを中心に、実践も交えながら、正しいフィードバック手法を身につけます。
フィードバックとは「現実と向き合う機会を提供すること」
フィードバックは、客観的な視点を与えることで、部下や後輩が自らの状況を正確に把握し、現状からの成長を目指すキッカケをつくるものです。まずは現時点における改善点や必要な取り組み、そして相手に対する期待を正しく伝えることが、フィードバックのゴールとなります。正しい手法でフィードバックができれば、厳しい指摘も含めて、それぞれが現実と向き合う機会にすることが可能です。そして効果的なフィードバックを通じて、部下や後輩が自分自身の立ち位置を理解し、今どう行動すべきかを自ら判断して実行に移すことで主体的な成長につながります。
まとめ
より効果的なフィードバックができれば、部下や後輩の主体的な行動を促し、さまざまな経験や学びを得て成長するキッカケにもなるものです。反対に、中身のない漠然としたフィードバックは、部下や後輩の意欲を低下させるだけでなく、上司としての信頼を下げる可能性もあります。そこで本研修では、部下や後輩の成長につなげるための正しいフィードバック手法の習得が可能。一人ひとりが自ら理想のキャリアパスを叶えようとする、キャリア自律を促すフィードバック手法を身につけることができます。こうしたキャリア自律に直結した人材育成にもつながる、質の高いフィードバックに向けて、ぜひ本研修をご活用ください。
◆本記事でご紹介した研修
フィードバックの基本(136)