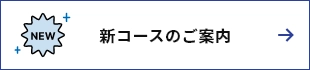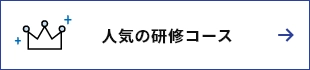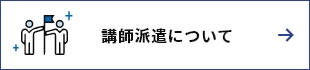“恒例行事”で終わりがちな人事評価を組織力アップの手段に! 管理職のための評価の基本研修とは?
- 記事公開日
- 2025.09.02

この記事のポイント
人事評価とは、ただ各メンバーの能力や実績を見極めるのではなく、本来は組織としての業績アップや人材育成の促進を目的として実施するものです。実際の評価や考課面談は、あくまで組織力を高める手段であり、新たなステップにつながるように運用する必要があります。
この記事では、3時間で学べる研修「管理職研修 評価の基本(178)」の内容をご紹介します。
考え方の偏りが効果的な人事評価の妨げになる
メンバーの成長や生産性向上に向けて、より的確な人事評価をするためには、事実やデータにもとづき項目ごとに公平な視点で個々の実績を見極めることが重要。例えば目標達成率など、数値化できる項目では客観的な判断がしやすいでしょう。一方で、人事評価における行動や過程などの定性的な要素では、判定者の主観が入るのは避けられません。個人の主観により事実の捉え方や相手に対する期待値なども変わってくる影響から、判定者ごとに最終的な見解には差が出やすく、また考え方の偏りから正確な評価ができていない場合も見られます。
効果的な人事評価のためには、自身の主観を冷静に分析し、自らの考え方の癖を知っておくことも必要です。また正しい判断による人事評価ができることで、組織全体への次のような効果にも期待できます。
偏りのない人事評価から見込めるメリット
的確な人事評価によって社員の成長やモチベーション向上を促進できれば、個々の帰属意識も高まり、優秀な人材の定着・キャリア形成にもつながります。さらに人事評価の仕組みが整っていることで、社員を大切にする姿勢によるイメージアップもでき、入社希望者の増加など人材確保も促進。このように自社の人材が豊富になれば、仲間同士で刺激し合う環境も生まれやすく、組織の活性化や新たな企業文化の醸成などにも期待できます。こうして組織全体の生産性が向上できれば、企業としての発展や目標達成なども実現しやすくなります。
正しい人事評価により一人ひとりのパフォーマンスを最大化
正しい人事評価から業務遂行や能力開発における課題の可視化・改善を図り、より最適な育成・人材活用・公正な処遇を実現させることは、一人ひとりの成長やモチベーション向上を促します。こうして個々の力を最大限に引き出し、それぞれのパフォーマンスを高めることで、業績向上やビジョンの実現など組織としての成果にも結び付きます。そこで研修では、このような人事評価に向けて、身につけておきたい基礎知識を習得。以下のような、評価のゆがみを引き起こす事例をもとに、正しい人事評価をしていくためのポイントを学びます。
評価をゆがめてしまいやすい思考の傾向例
人事評価において、公平な視点による的確な判断を欠いてしまいやすい思考として、以下のようなパターンが挙げられます。
- ハロー効果:各人材の特定の優劣点によって各項目の評価も左右されてしまう(例:「○○ができていないから全体の評価も低いだろう」)
- 寛大化傾向:客観的事実のない過大評価(例:「いつも頑張っているから高めの点数にしてあげよう」)
- 厳格化傾向:自身の実績との比較や先入観による過小評価(例:「普通なら△△はできて当たり前だから加点にはならないだろう」)
- 中心化傾向:評価の根拠があいまいで、各人材や項目ごとに優劣の差を付けられない(例:「大きな失敗はないから平均点にしておこう」)
- 極端化傾向:評価のメリハリを意識するあまり、根拠のない差を付けてしまう(例:「○○の項目で点数が高めだから、△△では下げておこう」)
- 論理誤差:各項目の関連性や類似性からの推測による評価(例:「○○ができているなら、△△も同じく評価できるだろう」)
- 対比誤差:自身の得意・不得意を基準とした、自らの特性と反する評価(例:「自分の苦手な○○ができるから高く評価しよう」)
- 近接誤差:直近の実績に大きく左右された評価(例:「ラストスパートで巻き返したから評価も高めでいいだろう」)
- ステレオタイプ:各人材の実績や成果に関係ない属性や特性にもとづく評価(例:「○○大学を出ているから高めの評価になるだろう」)
本研修では、上記のような人事評価における偏った判断をしていないか、自分自身の考え方の振り返りをしていきます。
本研修で習得できる人事評価のポイント
本研修にて人事評価の基礎知識から学ぶ効果として、次のような受講者の声も上がっています。
- 評価者として、部下のモチベーションのアップや「評価は公平であるべき」など、これまで忘れていた項目を再確認できました。これまでの経験と受講した内容を自分なりに振り返り、良かった点、悪かった点の洗い出しができたことは価値があります。
- 目標設定の段階で、期末の評価ポイントを踏まえた部下とのコミュニケーション(認識合わせ)や部下のモチベーション向上、組織力向上のバランスをうまく取れるような評価の手法を学ぶことができました。
本研修では、評価のエラー事例にもとづいた個人ワークやループワークを通して、自らの考え方を見つめ直しながら、正しい人事評価に向けて注意したいポイントを学習できます。
まとめ
人事評価は、単純に評価して終わりではなく、組織としての成長を見越して運用していく目的があります。そこで本研修では、確かな成果を生み出す組織力につながる、より的確な人事評価のための基礎知識を習得していきます。各人材のさらなる活躍に向けた、人事評価の手法を身につけたい場合には、ぜひ本研修を活用してみてください。
◆本記事でご紹介した研修